Step2:基準階に共用部分を配置する
次に共用部分を配置します。事務所の共用部分は、一般的には次のような用途の部分を指します。
・階段室、エレベーター、エレベーターホール、廊下、便所、湯沸室、空調関係機械室、各種シャフトスペース
建物の規模にもよりますが、共用部分は基準階の面積の15%〜25%程度を占め、屋内に配置されるのが通常で、住宅のように共用廊下等の容積率不算入措置もありませんので、賃貸有効面積に直接影響を与えます。
共用部分をどこに配置するのかは判断の難しいところですが、鑑定評価の建物想定においては、とりあえず建物の片側に確保しておき、テナント割りを考慮して適宜移動するなど調整すればよいでしょう(図3参照)。また、建物の高さが31m(基準階階高3.6mとすると、9階で必要)を超えると非常用エレベーター※6が必要になりますし、地下3階以下及び地上15階以上の階には特別避難階段※7が必要ですので注意して下さい。
基準階のプランが完成しましたら、当該プランを各階層にコピーし、1階についてはエントランスなどを配置します。
|
|
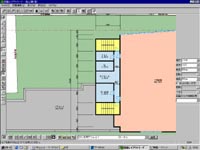 |
| ◆図3:共用部分配置例 |
|
|
|
Step3:駐車場を配置する
事務所ビルを想定する上で忘れてはいけないのが駐車場の確保です。地方自治体の多くで駐車場条例により最低限確保すべき台数を定めていますが、このいわゆる法定台数と実際に必要となる台数とは必ずしも一致しません。
都心の事務所ビルの場合は、地下鉄等の公共交通機関の利便性が高いことから比較的少なくてすみますが、地方都市や郊外型の事務所ビルでは、自動車の利用率が高く法定台数では収容しきれません。必要駐車台数の想定に当たっては、対象地の立地等を十分に考慮して、想定する必要があります。
駐車場は、屋外駐車場を確保できるのであればコストを低く抑えることができますが、事務所ビルを想定するような敷地においては無理な場合が多く、独立またはビル内組込式の立体駐車場や地下などの機械駐車場を想定することになります。
駐車場の設備については車路幅や回転半径、1台当たりの駐車面積など、様々な基準があり、ゼロから想定するのは非常に大変です。しかし、TP−PLANNERでは、代表的な駐車場の形式毎に駐車場のパターンを登録し、必要に応じて登録したパターンを呼び出すといった使い方ができることから非常に効率的に駐車場を想定することができます |
|
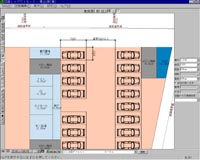 |
| ◆図4:駐車場配置例 |
|
|
|
Step4:使用容積率チェック
各階層のプランができたら使用容積率をチェックします。使用容積率が基準容積率を満たしていない場合には、斜線断面図などを利用して基準階より上層で部屋となる空間を確保し忘れていないかをしっかりと確認します(図5参照)。
Step1で述べましたが、事務所ビルの建物形状は、ほぼボリュームチェックによって把握される建築可能空間に近いものとなります。そのため、共同住宅の場合と異なり、L字型に住戸の配置を検討する作業はありませんので、この段階で作業は完了します。
|
|
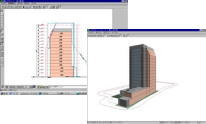 |
| ◆図5:上部空間を斜線断面図と立体図でチェック |
|
|
|
3.次回のテーマ
以上が鑑定評価で事務所ビルを想定する手順となります。
3回続けて建物のプランニングについて説明してきましたが、次回は傾斜地などに建物を想定する場合に留意すべき事項を説明します。
※記事中の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。また、各種規制については一般的基準であり、別途強化規定・緩和規定が存在する場合がありますので、ご注意下さい。
|
